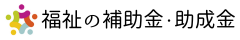障害者雇用とは、文字通り障害者を雇用することをさします。現代の日本では、障害者雇用は障害者手帳を持った方を雇用することであり、法令上の義務とされていますが、近年では、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進、そして企業の社会的責任(CSR)を果たすための要素として扱われるなど単なる義務にとどまらない関わり方が求められています。
本稿では、障害者雇用の根幹をなす理念と法制度から、企業が直面する具体的な義務、活用可能な経済的支援、そして真にインクルーシブな職場を構築するための実践的なアプローチや活用できる補助金まで、専門的な視点から網羅的に解説します
1.障害者雇用とは?理念と法的基盤

障害者雇用制度を理解するためには、まずその背景にある理念と法律の枠組みを把握すると全体像がつかみやすくなります。この章では、制度の定義からその哲学的・法的根拠までを掘り下げます。
障害者雇用の定義:法定雇用率制度を超えて
障害者雇用とは、正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下、障害者雇用促進法)に基づき、民間企業や国、地方公共団体などの事業主に対して、雇用する労働者の総数に一定の割合(法定雇用率)を乗じた人数以上の障害者を雇用することを義務付ける制度です 。
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
障害者雇用促進法の基本原則
障害者雇用促進法は、いくつかの重要な原則に基づいています。これらは、企業が障害者雇用に取り組む上での行動指針となります。
- 目的(第1条):この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進、職業リハビリテーションの推進、その他障害者がその能力に適合する職業に就くことを通じて職業生活における自立を促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的としています 。
- 事業主の責務:すべての事業主は、「社会連帯の理念」に基づき、障害のある労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に協力する責務を有します。これには、その能力を正当に評価し、適切な雇用の場を提供するとともに、適正な雇用管理を行うことが含まれます 。
- 差別の禁止:募集、採用、賃金、配置、昇進など、雇用に関するあらゆる局面で、障害があることを理由とする差別は明確に禁止されています 。
- 合理的配慮の提供義務:事業主には、障害のある労働者が職場で能力を発揮する上で障壁となる事柄を取り除くため、過重な負担にならない範囲で、必要な変更や調整を行う「合理的配慮」を提供する義務が課せられています 。この重要な概念については、第4章で詳述します。
歴史的変遷:よりインクルーシブな制度へ
現在の障害者雇用制度は、一朝一夕に形成されたものではありません。その歴史は、社会の障害に対する理解の深化を反映しています。
制度の源流は、1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」にあります。これは主に、第二次世界大戦によって身体に障害を負った人々の雇用を促進することを目的としたものでした 。
その後、制度の対象は段階的に拡大されてきました。
- 1987年:法律の名称が現在の「障害者雇用促進法」に改められ、対象に知的障害のある人が加えられました 。
- 2018年4月:精神障害のある人が法定雇用率の算定基礎に完全に対象として加えられました。これは、それまでの段階的な導入期間を経ての大きな前進でした 。
この歴史的変遷は、単なる対象範囲の拡大以上の意味を持ちます。それは、障害者雇用政策が、戦後の福祉的措置から、より普遍的な人権と社会参加を保障する経済政策へと進化したことを示しています。
当初の特定の歴史的背景を持つ集団への対応から、知的障害、そして精神・発達障害を含む、より広いスペクトラムの障害を包摂するようになったことは、障害を個人の問題ではなく社会全体の課題として捉えるという哲学的な転換を物語っています。
「差別の禁止」や「合理的配慮」といった概念の導入は、この転換を法的に裏付けるものであり、もはや「雇用するか否か」だけでなく、「雇用した後にいかに公正に処遇し、活躍を支援するか」が問われる時代になったことを明確に示しています。この進化の軌跡は、今後も企業に求められる社会的期待が、より一層高度化していくことを示唆しています。
2.法定雇用率実践ガイド

障害者雇用の重要性はわかってはいても、人事担当者にとって、障害者雇用を実際に導入することは、なかなかハードルが高いです。特にこれまで障害者との関りがなかった企業にとっては、対応のためのコスト等を考えると、なかなか踏み出せないという方も多いと思います。ここでは、障害者雇用についての具体的な算定方法についても解説しながら、実務上の注意点を詳説します。
企業の義務:現在および将来の法定雇用率
障害者雇用については、企業規模等によって、一定の法廷雇用率が定められています。
- 現在の法定雇用率(2024年4月時点)
- 民間企業:2.5%
- 国・地方公共団体:2.8%
- 都道府県等の教育委員会:2.7%
- 将来の引き上げ(予定)
- 民間企業の法定雇用率は、2026年7月より2.7%に引き上げられることが決定しています 。これは、政府が継続的に障害者の雇用機会を拡大していくという明確な意思表示です。
- 義務の対象となる事業主
- 法定雇用率が2.5%の現在、常時雇用する労働者(従業員)が40.0人以上の民間企業は、障害者を1人以上雇用する義務があります 。
- この義務対象の範囲は、法定雇用率が2.7%に引き上げられると、従業員37.5人以上の企業へと拡大します 。
この法定雇用率の段階的な引き上げと、それに伴う義務対象企業の拡大は、一過性の変更ではなく、計画的な政策です。これにより、これまで対象外であった中小企業が次々と制度の対象に含まれることになります。
特に従業員数が30人から50人規模の企業は、もはやこれを「大企業の問題」と捉えることはできず、近い将来の義務化を見据えた計画的な準備が不可欠となっています。
雇用義務人数の計算方法
企業が雇用すべき障害者の人数(法定雇用障害者数)は、以下の計算式で算出します 。
法定雇用障害者数=(常時雇用労働者数+(短時間労働者数×0.5))×法定雇用率
- 用語の定義
- 常時雇用労働者:週の所定労働時間が30時間以上の労働者 。
- 短時間労働者:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者 。
- 重要な注意点:計算結果に生じた小数点以下の端数は、切り捨てとなります 。
- 計算例
- A社(従業員100人):常時雇用労働者50人、短時間労働者50人の場合 (50+(50×0.5))×0.025=75×0.025=1.875 小数点以下を切り捨てるため、雇用義務人数は1人となります 。
- B社(従業員200人):常時雇用労働者150人、短時間労働者50人の場合 (150+(50×0.5))×0.025=175×0.025=4.375 小数点以下を切り捨てるため、雇用義務人数は4人となります 。
障害者雇用の実人員計算
実際に雇用している障害者の数を算定(カウント)する際には、単純な頭数ではなく、障害の種類や程度、労働時間によって換算方法が異なります。
- 対象者の条件:カウントの対象となるのは、原則として既定の障害者手帳等を所持している方に限られます。具体的には、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害)、または精神障害者保健福祉手帳のいずれかです 。
- 障害者1人あたりのカウント換算表(2024年4月時点) 人事担当者が自社の実雇用率を正確に把握するためには、雇用における換算ルールを理解することが不可欠です。下記の表は、ルールを一覧化したものです。
- 例えば、重度の身体障害がある方を1人常勤で雇用した場合(カウント2.0)は、重度でない方を短時間で雇用した場合(カウント0.5)の4倍、雇用率に貢献することが一目でわかります。
| 障害の種類 | 週30時間以上 | 週20時間以上30時間未満 | 週10時間以上20時間未満 |
| 身体・知的障害(重度以外) | 1.0人 | 0.5人 | 対象外 |
| 身体・知的障害(重度) | 2.0人 | 1.0人 | 0.5人 |
| 精神・発達障害 | 1.0人 | 1.0人(特例措置) | 0.5人 |
精神・発達障害者のカウントルール
精神障害者(精神障害者手帳保持者)については、雇用促進するため、特例的な算定方法が設けられています。
- 短時間労働者の特例:上表の通り、週20時間以上30時間未満で働く精神障害のある方は、本来0.5人とカウントされるところを、当分の間1.0人として算定できます。これは、比較的短い労働時間から就労を開始することが多い精神障害のある方の雇用を後押しするための重要な政策的措置です 。
- 超短時間労働者の算定対象化:2024年4月から、これまで算定対象外であった週10時間以上20時間未満で働く労働者についても、重度の身体・知的障害、または精神障害のある場合は0.5人としてカウントできるようになりました 。これは、障害特性により長時間の勤務が困難な方々に対して、より柔軟な働き方の選択肢を提供することを目的とした画期的な改正です。
3.経済的枠組み:納付金、調整金、助成金
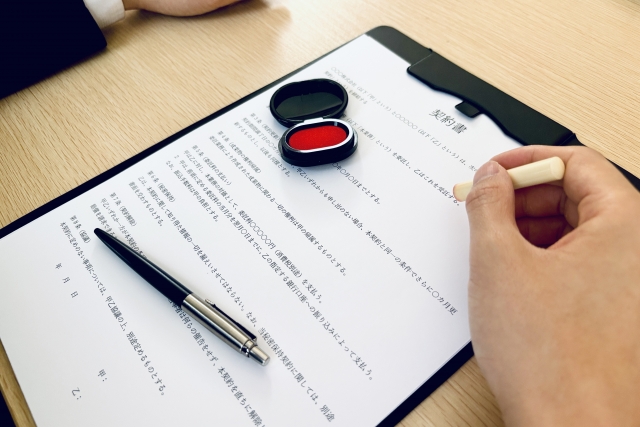
障害者雇用制度は、社会的にも意義がある制度ですが、企業にとっては負担に感じる場合もあります。また、状況によっては障害者雇用が難しい場合があったり、敢えて障害者を雇用しないといった企業もあります。障害者雇用制度は、こういった不平等是正のために罰則や給付金制度を定めています。
障害者雇用納付金
常時雇用する労働者が100人を超える企業が法定雇用率を達成できなかった場合、不足する人数に応じて障害者雇用納付金を納める義務が生じます 。
障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
- 金額:不足1人あたり月額50,000円 。
- 納付金の位置づけ:納付金は「罰金」ではありません。障害者雇用という社会的責任を果たしている企業と、そうでない企業との間に生じる経済的な負担の不均衡を調整するための制度です 。集められた納付金は、後述する調整金や助成金の原資となります。
- 不履行の場合:納付を怠ると、督促や、最終的には財産の差し押さえといった強制措置に至る可能性があります 。
調整金と報奨金
反対に、制度にそって障害者を雇用している企業に対しては、障害者雇用調整金などが給付されます。
- 障害者雇用調整金
- 対象:常時雇用労働者が100人を超える企業で、法定雇用率を超過して障害者を雇用している場合 。
- 金額:超過1人あたり月額29,000円 。
- 近年の変更点(2024年4月〜):超過人数が月10人を超える部分については、支給額が月額23,000円に調整されます 。
- 報奨金
- 対象:常時雇用労働者が100人以下の企業で、一定数を超えて障害者を雇用している場合 。
- 金額:対象となる超過1人あたり月額21,000円 。
- 近年の変更点(2024年4月〜):年間の支給対象人数が35人を超える部分については、支給額が月額16,000円に調整されます 。
この調整金・報奨金の支給額調整は、単なる財政上の措置ではありません。障害者雇用者数が過去最高を更新し続ける中で、調整金等の支給対象となる企業が増加し、納付金制度の財源が逼迫しつつあるという背景があります。
この課題に対し、政府は納付金の額を引き上げるのではなく、すでに多数の障害者を雇用している企業への支給額に上限を設けるという選択をしました。これにより捻出された財源は、トライアル雇用助成金など、これから障害者雇用を始める企業、特に中小企業にとって利用しやすい支援策に振り向けられると考えられます。これは、一部の先進企業にさらに報いるのではなく、制度全体の裾野を広げ、より多くの企業の参加を促すという戦略的な政策転換の表れです。
参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」
企業の取り組みを支える各種助成金
納付金制度とは別に、障害者雇用の各段階(雇入れ、定着、環境整備など)を支援するための多様な助成金制度が用意されています。
| 項目 | 制度名 | 対象事業主 | 条件 | 金額 |
| 未達成時の負担 | 障害者雇用納付金 | 従業員100人超 | 法定雇用率未達成 | 不足1人月額5万円 |
| 超過達成時の奨励 | 障害者雇用調整金 | 従業員100人超 | 法定雇用率超過 | 超過1人月額2.9万円(10人超分は2.3万円) |
| 超過達成時の奨励 | 報奨金 | 従業員100人以下 | 一定数を超えて雇用 | 超過1人月額2.1万円(年35人超分は1.6万円) |
| 雇入れ支援 | 特定求職者雇用開発助成金 | 全事業主 | ハローワーク等の紹介で就職困難者を継続雇用 | 1人あたり30万~240万円 |
| 雇入れ支援 | トライアル雇用助成金 | 全事業主 | 3ヶ月間の試行雇用 | 1人あたり月額最大4万円 |
| 定着支援 | キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) | 全事業主 | 有期雇用から正規・無期雇用へ転換 | 1人あたり33万~120万円 |
| 職場支援 | 職場支援員の配置助成金 | 全事業主 | 職場支援員を配置 | 月額1.5万~4万円 |
| 職場支援 | 職場復帰支援助成金 | 全事業主 | 中途障害者の職場復帰を支援 | 月額4.5万~6万円 |
障害者雇用を通じてインクルーシブな職場を造成する

障害者雇用を法定雇用率に沿って達成することは、時にハードルが高いことに感じられるかもしれません。しかし、障害者雇用は、単なる障害者雇用にとどまらず、誰もが働きやすい職場や社会を実現するといったインクルーシブな土壌を造成します。
ここでは、障害者雇用と通常の企業活動を両立していくためのポイントを解説します。
合理的配慮をどうおこなっていけばいいのか
障害者雇用をする上で欠かせないのが、合理的配慮です。合理的配慮は、障害のある従業員が他の従業員と平等に能力を発揮できるよう、職場における物理的・制度的な障壁を取り除くための、個別の調整や変更を指します。ただし、その提供が事業主にとって「過重な負担」とならない範囲で行われるものとされています 。
合理的配慮とは、
・募集及び採用時においては、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保する
ための措置
・採用後においては、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の
能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置
のことをいいます。
最も重要な点は、合理的配慮が一方的な提供物ではなく、事業主と障害のある従業員との間の対話を通じて決定されるという点です。どのような配慮が必要かは、個人の障害特性や職場の状況によって千差万別であるため、相互理解に基づいた建設的な話し合いのもとに行わることが期待されています。
合理的配慮の具体例
以下に、障害の種類に応じた合理的配慮の具体例を挙げます。
- 視覚障害:採用試験を点字や音声で実施する、業務資料を拡大文字や音声読み上げソフトで提供する、通路の安全を確保し危険箇所を事前に伝える 。
- 聴覚・言語障害:面接や業務指示を筆談やメール、チャットツールで行う、必要に応じて手話通訳者を配置する、火災報知器などを光で知らせる視覚的な警報装置を設置する 。
- 肢体不自由:机の高さを調整可能なものにする、スロープや手すりを設置して移動を容易にする、在宅勤務など柔軟な勤務場所を認める、通勤用の駐車場を確保する 。
- 知的障害:作業手順を図や写真を多用したマニュアルで示す、指示は一度に一つずつ明確に伝える、チェックリストを用いて進捗を確認する、相談役となる担当者を決める 。
- 精神・発達障害:
- 柔軟な勤務:通院や体調に合わせて出退勤時間や休憩時間を調整する、フレックスタイムや在宅勤務を許可する 。
- 明確なコミュニケーション:業務の指示やスケジュールを具体的に、かつ構造化して伝える。口頭の指示をメールやチャットで補足する 。
- 環境調整:感覚過敏を緩和するため、静かな休憩スペースを提供する、サングラスやノイズキャンセリングイヤホンの使用を認める 。
- 業務調整:本人の状況を見ながら業務量を調整する、業務の優先順位を明確にする 。
合理的配慮の制定は、障害者の特性によって様々であり、障害者と対話を通じて個別の課題を解決するというぷろせすが 必要不可欠です。しかしその過程は、本質的に優れたコミュニケーションと問題解決の実践に他なりません。
例えば、発達障害のある従業員のために明確で構造化された指示方法を学ぶ管理職は、結果的にすべての部下にとってより良い管理職になります。また、業務フローを見直してアクセシブルにすることは、しばしば組織全体の非効率性を発見し、改善するきっかけとなります 。したがって、合理的配慮は特定の従業員のためのコストではなく、組織全体のマネジメント能力と生産性を向上させるための投資と見なすことができます。
D&I、イノベーション、CSRの推進
障害者雇用は、場合によっては企業にとってデメリットに移ることもあるかもしれません。しかし、障害者雇用制度への真摯な取り組みは、コンプライアンスを超えた多くの戦略的メリットを企業にもたらします。
- D&I文化の醸成:多様な背景を持つ人材を積極的に受け入れ、支援するプロセスを通じて、組織全体の柔軟性や共感性が高まります。これは、すべての従業員にとって働きやすい職場環境の構築につながります 。
- 業務改善とイノベーションの促進:障害のある従業員が直面する課題を解決するために業務プロセスを見直すことは、しばしば組織全体の非効率な点を浮き彫りにし、業務の標準化や効率化を促すきっかけとなります 。
- 企業価値とCSRの向上:障害者雇用に積極的に取り組む姿勢は、企業の社会的価値を内外に示す強力なメッセージとなります。ブランドイメージの向上、投資家や顧客からの信頼獲得に繋がり、公共入札などで有利に働くこともあります 。
- 人材獲得と市場拡大:これまで見過ごされてきた優秀な人材層にアクセスできるようになります。また、障害のある従業員の視点は、多様な顧客ニーズに応える新しい製品やサービスの開発に繋がる貴重なインサイトを提供します 。
障害者雇を成功させるための重要な要素とは
障害者雇用を成功させている企業には、共通する特徴が見られます。
- 経営層のコミットメント:トップが明確なビジョンを持ち、全社的な取り組みとして推進する 。
- 計画的な採用:場当たり的な採用ではなく、明確な採用基準と計画に基づき、戦略的に雇用を進める 。
- 社内理解の促進:全従業員を対象とした研修などを通じて、障害に関する正しい知識を共有し、偏見をなくす努力をする 。
- 外部支援機関の活用:ハローワークや地域障害者職業センター、就労移行支援事業所などの専門機関と積極的に連携する 。
- 職場実習の導入:本格的な採用の前に、職場実習やトライアル雇用を活用し、本人と企業の双方にとって最適なマッチングを図る 。
障害者雇用は、ときに通常の従業員の雇用以上に、組織全体でのダイナミックなアクションが必要となります。そのため、経営層もしっかりと環境作りなどのプロセスに関わり、社内外の資源を有効に活用することが重要です。
5.障害者雇用の求人方法

障害者雇用を成功させるためには、自社にマッチした人材をいかに獲得するかが非常に重要です。障害者雇用の場合は、通常の求人とは違った採用ルートが存在します。自社にあった人材を獲得するためにも、障害者特有の制度などを把握しておくといいでしょう。
障害者が使う求人情報は?
障害者の場合は、通常の採用サイトやエージェントの他にも、就労移行支援事業所などが採用のために重要なルートになります。
| 求人情報の種類 | 主な特徴 | 想定される利用方法 |
| ハローワーク(公共職業安定所) | 国の公的機関で利用は無料。障害者専門の窓口があり、専門知識を持つ職員が対応。求人数が豊富で、地域に密着した求人が多い。「トライアル雇用」の紹介や、面接への同行支援も実施。 | 幅広い求職者の閲覧に期待できるため、オープンに様々な障害者を採用したいという場合にむいています |
| 就労移行支援事業所 | 障害者総合支援法に基づく福祉サービス。最長2年間、就労に必要なスキル(PC、ビジネスマナー等)の訓練、生活リズムの構築、職場実習などを提供。就職活動から就職後の定着支援まで一貫してサポート。 | 就労移行支援事業所は、以前は就労していた方、一般就労も目指すような方なども多いのが特徴です。就労移行支援事業所側でも、求人の開拓は行っていますので、地域の就労移行支援事業所などに声をかけてみるといいでしょう。 |
| 特別支援学校 | 心身に比較的重度の障害がある子どもたちが、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けながら、障害による困難を克服し、自立するための知識や技能を学ぶ学校です。 | 特別支援学校は、障害の種類や程度は様々ですが、年齢が若い求職者からの応募に期待できます。そのため、長期的な計画にそって採用を行いたいという場合におすすめです。 |
| 民間転職エージェント | 民間企業が運営する専門的な就職・転職支援サービス。非公開求人や専門職の求人を多く保有。キャリアカウンセリング、書類添削、面接対策など、個別のニーズに合わせた手厚いサポートが特徴。障害種別や業界に特化したエージェントも多数。 | ある程度の職務経験やスキルがあり、より専門的な職種やキャリアアップを目指す方が多いです。専門職など、条件が絞られる求人は、転職エージェントを頼りにするといいでしょう。 |
| 地域障害者職業センター・障害者就業・生活支援センター | 国や自治体が設置する公的機関。ハローワーク等と連携し、専門的な職業評価、職業準備支援、ジョブコーチによる職場適応援助などを提供。就業面と生活面を一体的に支援する「なかぽつ」もある。 | 職業能力の客観的な評価を受けたい方、就職だけでなく生活面も含めた包括的な支援が必要な方、職場定着に専門的な支援(ジョブコーチ等)を要する方。 |
害者雇用制度は、着実な成果を上げている一方で、新たな課題にも直面しています。この最終章では、最新の統計データを基に現状を分析し、残された課題と、今後の制度の方向性について考察します。
6. 日本における障害者雇用の現状

厚生労働省が発表した令和6年(2024年)の「障害者雇用状況の集計結果」は、制度の進展を示す明るい側面と、新たな課題を浮き彫りにする側面の両方を示しています。
- 過去最高の雇用者数:民間企業に雇用されている障害者の数は、前年比5.5%増の677,461.5人となり、21年連続で過去最高を更新しました 。また、企業が実際に雇用している障害者の割合を示す実雇用率も、過去最高の2.41%に達しました 。
- コンプライアンスのパラドックス:一方で、法定雇用率(2.5%)を達成した企業の割合は46.0%と、前年から4.1ポイント低下しました 。これは、雇用者数が増えているにもかかわらず、法定雇用率そのものが引き上げられた(2.3%→2.5%)ことで、達成のハードルが上がったことを示しています。
- 業界による格差:「医療、福祉」分野の実雇用率が3.19%と突出して高いなど、業界による取り組みの差も見られます 。
参考:障害者雇用状況の集計結果
残された課題:定着、キャリア形成、職種の偏り
数字の上での成功の裏で、雇用の「質」に関する課題は依然として根深く残っています。
- 定着率の問題:特に精神障害のある方の場合、就職後1年での定着率が50%を下回るという厳しいデータがあります 。離職の主な理由としては、職場での人間関係や、任される仕事内容とのミスマッチ(難しすぎる、または簡単すぎてやりがいがない)が挙げられています 。
- 質の格差:障害者雇用枠での求人は、事務補助や清掃といった特定の職務に偏る傾向があり、非正規雇用が多いのが実情です。これにより、賃金が低水準に留まったり、キャリアアップの道筋が見えにくかったりする問題が生じています 。障害のある従業員が、企業の基幹的な人材育成のラインから外れた「サイロ」に置かれてしまうリスクも指摘されています 。
- 採用における偏見:企業側が「管理しやすい」と考える特定の障害種別に採用が偏る傾向も依然として存在し、障害種別による機会の不均衡を生んでいます 。
この現状は、障害者雇用制度が重大な転換点にあることを示唆しています。雇用者数という「量的」な成功は、定着率の低さやキャリアの停滞といった「質的」な課題を覆い隠しています。
今後の政策や企業の戦略は、この「質のギャップ」を埋めることに焦点を当てる必要があります。単純な事務作業の切り出しといった手法だけでは限界が見えており、障害のある人材をいかにして組織のコア業務に統合し、長期的な戦力として育成していくかという、より高度な戦略が求められる段階に来ています。
事例紹介
課題は多いものの、多くの企業が創意工夫を凝らし、障害者雇用を成功させています。厚生労働大臣表彰などを受けた優良企業の事例は、具体的なモデルとして大いに参考になります。
- 株式会社仙台にしむら(マクドナルド・フランチャイズ):障害のある従業員を「チャレンジクルー」と呼び、本人の希望を尊重した業務配置を行う。タブレット端末による作業学習や、ジョブコーチによるキャリアアップ支援など、個々の成長を促す仕組みを構築している 。
- SMBCグリーンサービス株式会社:精神障害のある方の雇用に特化し、短時間勤務制度や手厚い相談体制を整備することで、高い定着率と安定した就労を実現している 。
- 株式会社オープンハウスグループ:正社員登用を積極的に行い、70種類以上の多様な業務を提供。チームで業務を遂行する体制を築き、個々のキャリアパスを拓いている 。
- ライオンともに株式会社(ライオン株式会社の特例子会社):障害のある従業員が、製品開発に不可欠な実験器具の洗浄業務などを担当。企業の基幹プロセスに深く関与し、重要な戦力となっている 。
これらの事例は、飲食、金融、不動産、メーカーといった多様な業界で、障害種別を問わず成功が可能であることを示しています。
今後の展望:法改正と社会の変化がもたらす未来
障害者雇用を取り巻く環境は、今後も変化し続けます。
- 継続的な法定雇用率の引き上げ:2026年に予定されている2.7%への引き上げは、さらに多くの中小企業を制度の対象とし、人事戦略における障害者雇用の重要性を一層高めるでしょう 。
- 「量」から「質」への転換:政策の議論は、徐々に「何人雇用したか」から「いかに定着し、活躍しているか」へとシフトしていくと予想されます。将来的には、定着率や昇進率といった質的な指標がより重視される可能性があります。
- D&I経営の必須要素として:ダイバーシティ&インクルージョンが企業経営の中心的な価値観となる中で、障害者雇用はもはや独立したコンプライアンス課題ではなく、多様で強靭な組織を構築するための不可欠な要素として認識されるようになるでしょう 。
まとめ
障害者雇用は、単なる制度の枠内にとどまらず、誰もが働きやすい社会の実現にむけ、多様な人々の受け皿となる取り組みのひとつです。障害者雇用に興味をもっているという方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。