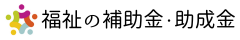| 助成事業者 | 大阪府 |
| 資金タイプ | 補助金 |
| 概要・補助対象事業 | イベント・セミナー等、新規事業・製品開発等、設備投資、運転資金・その他活動費等 |
| 内容 | 「大阪府福祉基金」は、府民の皆様からのご寄附を積み立てて運用している制度です。大阪府では、福祉の向上のために寄せられた温かいご厚志を踏まえ、この基金の運用益及び積み立てた基金を活用し、「地域福祉振興助成金」として、府民の自主的な社会福祉活動を支援しています。大阪府は府民の皆様が社会福祉活動を始めたり、継続することを応援します。
1.活動費助成
障がい者や高齢者、児童福祉の向上に寄与することを目的として実施する次のa~eに該当する事業(ボランティアによる草の根活動)
【助成額は20万円以内】
a:福祉活動機器購入(助成を受けた年度以降2年間は申請不可)
b:社会参加推進
c:講演会等開催
d:普及啓発(「普及啓発活動に要する印刷物、物品等の作成に要する経費」での助成は、助成を受けた年度以降2年間は申請不可)
e:その他(aからdに該当しない事業については、「その他」で申請して下さい。※助成対象とはならない事業は除く)
2.地域福祉推進助成「民間団体提案型事業」
府民福祉の向上に寄与することを目的として実施する「地域における連携、協働による事業」で、「先駆的、先導的及び発展性のある事業」、もしくは、「制度の谷間または制度が十分に機能していないため、支援が行き届いていない人を支援する事業(必要性、重要性、緊急性のあるもの)」で、民間団体の自由な提案による事業
【助成額は100万円から500万円以内】
3.地域福祉推進助成「施策推進公募型事業」
府民福祉の向上に寄与することを目的として実施する「地域における連携、協働による事業」で、「先駆的、先導的及び発展性のある事業」、もしくは、「制度の谷間または制度が十分に機能していないため、支援が行き届いていない人を支援する事業(必要性、重要性、緊急性のあるもの)」で、大阪府が予め設定したテーマに則した事業(令和7年度は下記6テーマ)
【助成額は500万円以内】
【つながる「居場所」づくり事業】
地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく地域共生社会の実現が求められています。 そのためには、地域住民、民間事業者、社会福祉法人、NPO、民生委員・児童委員、行政等といった多様な地域の構成員が個々に活動するのではなく、お互いの活動を知り、参画・協働をしていかなければいけません。地域共生社会の実現のためには、それぞれの地域で地域住民等は、具体的に参画・協働できる「仕組み」と、「対話・協議」によるプロセスを誰かに押し付けられるのではなく、自らつくっていくということが重要です。
以上のことから、「つながる」をテーマに多様な主体が意見を出し合いながら居場所を考える、プロセス重視の居場所づくりとして、採択団体を中心に、行政(福祉分野等)、地域住民、市民活動団体、企業、商店等といった福祉だけに限定しないメンバーで、地域生活課題を把握の上、自地域にあったメニュー(農業、ゲーム、スポーツ等)や、地域とのつながりが希薄な方が参加しやすいイベント等を考えながら、様々な立場にいる人々が出会い、参加する居場所の創出をめざす事業を募集します。
【地域における18歳以上のヤングケアラー支援事業】
○令和6年6月に子ども・若者育成支援推進法が改正され、ヤングケアラーを国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象として明記し、その中で18歳以上のヤングケアラーへの支援が都道府県の役割とされました。
○本府においては、18歳以上のヤングケアラーへの支援として、専門的な相談支援やピアサポート事業の実施を計画しており、地域で18歳以上のヤングケアラー支援を実施する団体と相互に連携することで、支援の充実を図ることができると考えています。
○ヤングケアラーやそのご世帯が抱える課題は様々であり、かつ、家庭内のことであるため表面化しにくい構造となっています。このため、安全安心な居場所や自分らしくいられる場所で出会う信頼できる大人が、普段の関わりや会話の中から困りごとを発見し、ヤングケアラーやそのご世帯の意向を確認しながら支援につなげていく必要がありますが、18歳以上の若者が安心して過ごせる居場所は少ない状況です。
以上のことから、具体的な支援の中心的役割を果たすことが期待される市町村での居場所づくりのモデルとなるよう、18歳以上のヤングケアラー支援を実施する団体を募集します。
【障がいのある方の文化芸術アーティスト挑戦創出プロジェクト】
万博において、国内外に向け、障がいのある人、ない人が混在するチームで作品を発表する機会や、障がいのあるアーティストの、唯一無二の独創性を発する作品を発表するなど、すでに活躍している一部の障がいのあるアーティストの文化芸術活動を発信するとともに、それをレガシーとして継承する予定としていますが、府内における障がいのあるアーティストの活動を、万博開催後に継続していく具体的な手法が確立されていません。
また、文化芸術活動は、アート分野のみならず、舞台芸術分野、音楽分野など様々あり、府内で障がいのあるアーティストの活動支援に取り組んでおられる個人、福祉サービス事業所、支援団体、中間支援組織なども複数あります。しかしながら、障がいのあるアーティストの活動を支援するには、日常の活動においてどのような支援手法があるか、また文化芸術市場に挑戦していくに当たって中間支援組織はどのような役割を担うことが可能か、また有効かなど、支援の手法は可視化、明確化されていないため、これまで日常の活動から市場に挑戦するまでのプロセスを踏める取組みを行っているところは限られてきました。
この度、万博のレガシーを継承し、引き続き障がいのあるアーティストが高みをめざして挑戦し続けていく環境を府内で根付かせていくため、支援の手法を可視化し、市場に挑戦するまでの幅広い視点で活躍できる場を多数創出するなど、障がいのあるアーティストのたかみをめざす挑戦を後押しし、万博のレガシーを継承する事業を募集します。
【地域における子ども食堂支援機関ネットワークモデル事業】
令和6年6月現在、大阪府内の子ども食堂の数は938件となっており、令和5年6月時点の757件から約1.3倍の数となっています。近年、子ども食堂の数は増加傾向にあり、この増加とともに、地域における子ども食堂のネットワークも形成されつつあります。
困窮世帯への食事提供、不登校児童生徒や課題を抱える子どもの居場所、孤食の解消の場、食育、地域交流の場など、子ども食堂は様々な意味で居場所としての重要性が増しています。子ども食堂の活動が多様化する一方で、子ども食堂の抱える課題(資金不足、人手不足、安定的な食材の調達手法、学校や地域とのつながり方、周知広報手法など)は多種多様にあり、継続した活動が懸念される状況です。
また、大阪府が令和5年度に実施した「子どもの生活に関する実態調査」では、子ども食堂の利用を希望するものの利用しない理由に、「どこにあるか分からないから」と答える方が一定数ありました。こうした状況を踏まえ、大阪府では、必要とする人がいつでも自由に子ども食堂を利用できるよう子ども食堂の活動を推進し、かつその活動が府内全域に広がるよう、地域で子ども食堂のネットワークを形成し、子ども食堂の安定的な運営をめざし、子ども食堂の課題解決に取組みつつ、子ども食堂の支援を実施する活動を支援します。
【ひきこもり支援に関する居場所等の社会資源の創出モデル事業】
ひきこもり状態にある方(当事者)は全国で推計146万人、15~64歳では50人に1人程度と言われています(※)。相談窓口は増えてきましたが、当事者が安心して過ごせる場所や、自らの役割を感じられる活動の機会は少ないのが現状です。
当事者への支援には、多様で複合的な課題を有するひきこもり当事者の心情を理解して自己肯定感を高めることが必要です。また、社会参加のきっかけとなる一人ひとりのニーズに合った社会資源も必要です。個別支援だけでなく集団的支援の場がある等、多様な社会資源があることで、当事者にとって支援の選択の幅が広がります。
以上のことから、ひきこもり支援について、当事者と地域の実情に応じた社会資源の創出と当事者への影響について調査する事業を募集します。
(※)内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査 」(令和4年度)
【地域における多職種連携による相談支援モデルの開発】
包括的な支援は、本人とその世帯の状況を包括的に捉えた上で、必要な支援を考えてくいく必要があり、複合化・複雑化した課題を抱える世帯には、様々な専門性を持つ支援者がチームとなって必要な支援を考えていくことが重要です。
市町村域では各相談支援機関による多機関協働が進められている一方、地域レベルで地域住民や地域で活動する多職種との連携を進めていくには、住民と専門職をつなぐコーディネーター役、事例の紐解きとアドバイスができる人材、気にかけ声をかけてくれる住民や、困りごとに寄り添ってくれる住民を増やしていく仕掛けといった様々な取組みが必要ですが、そのノウハウを有する団体は不足しています。
(※令和5年度に実施した重層的支援体制整備事業を実施している府内自治体への調査(回答数17/18市町)では、回答した17市町のうち10自治体が「地域のなかで横断的・越境的な取組みを実践してくれる人材の発掘・登用が課題」と回答)
これらの状況を踏まえ、地域における多職種連携による相談支援体制の充実につながるモデル事業に対し、助成を行います。 |
| 地域 | 大阪府 |
| 助成対象団体 | NPO、任意団体・ボランティア、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
| 主に対象となる福祉施設 | その他社会事業・スタートアップ等、一般・特定相談支援事業、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)、障害者雇用 |
| 分野 | その他、児童、地域、引きこもり、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
| 応募資格・対象者 | 大阪府内で社会福祉活動(障がい者や高齢者、児童などへの支援等、府民福祉の向上に寄与する活動等)を行っている営利を目的としない団体(以下、非営利団体という。)。(団体の定款等を定めている必要があります。)
活動費助成:社会福祉活動の実績のある非営利団体(法人格の有無は問いません。)
地域福祉推進助成:次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉活動の実績のある非営利団体の法人で法人設立後3年を経過(令和7年4月1日時点)している者(役員が2名以上となる法人)
ただし、提示するテーマに取り組む団体については、法人設立後3年未満であっても直近の活動実績や構成員の活動歴が3年以上である場合は可)
(2)前記(1)に該当する者が代表者となる2者以上の者で組織された共同体
※代表となる団体は、交付手続き、事業実施、完了報告等の一切について、(2)の共同体と同様に責務を負う旨ご留意ください。
※団体または団体の役員が次の各号のいずれにも該当しない団体。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。)
(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。)
(3)暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。)
(4)法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
(5)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する
納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者 |
| 最大助成金額 | 499万円 |
| 対象費用 | その他雑費・消耗品費、出展、会場費、委託、外注費、活動費、設備投資費、謝金(研修等) |
| 応募受付開始日 | 2025年01月06日 |
| 応募期限・締切日 | 2025年01月31日 |
| 申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
| 募集要項詳細ページ | https://www.pref.osaka.lg.jp/o090020/chiikifukushi/kikin/joseikinnnobosyuu.html |
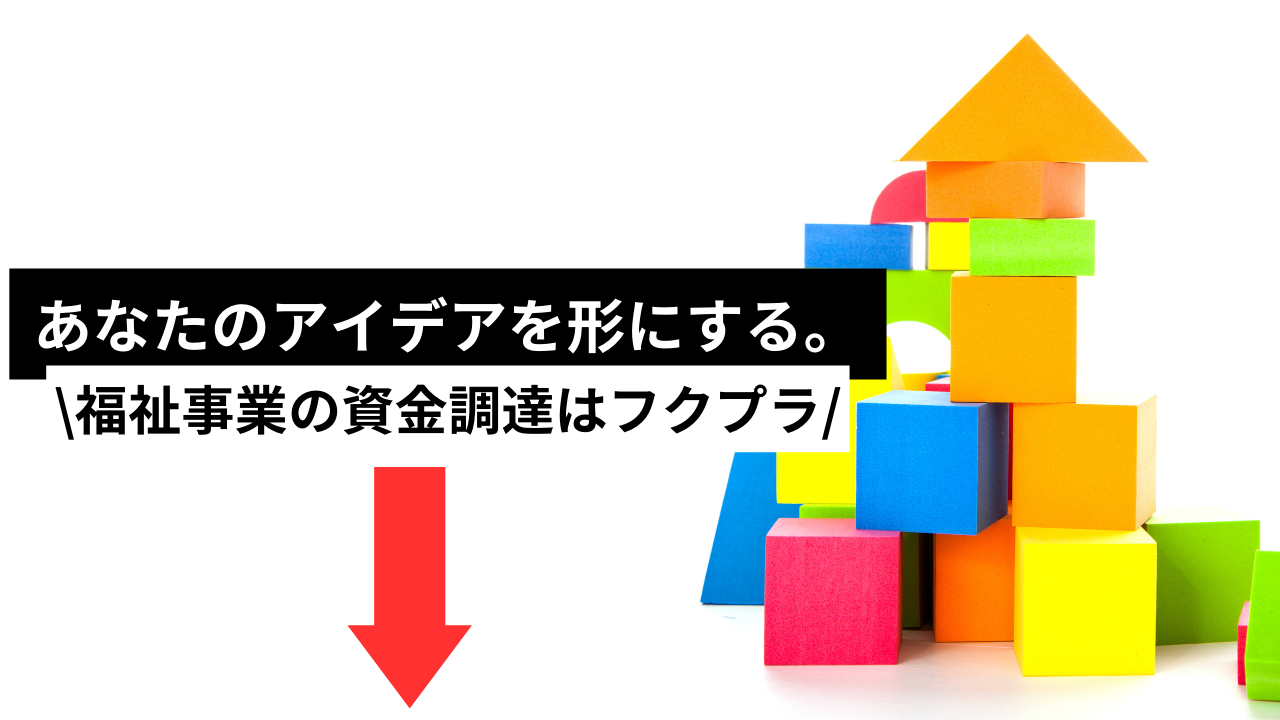 補助金・助成金
補助金・助成金