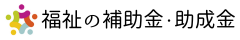福祉事業所というと、何か福祉的なサービスを提供するというイメージは湧くと思いますが、具体的にどういった施設かというところまではなかなかわかっている人はいないと思います。そこで、今回は福祉事業所の一覧や、第一種、第二種社会福祉事業の違い、根拠となる法律から概要まで、福祉事業所の全てを解説します。福祉事業所について知りたいという方は、本記事をみれば完璧です!
- 福祉事業所とは
- 第一種社会福祉事業
- 第二種社会福祉事業
- 第一種社会福祉事業・施設一覧(17事業)
- 第一種社会福祉事業一覧表
- 第2種社会福祉事業
- 生計困難者に、その住居で衣食その他日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
- 生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業
- 障害児通所支援事業
- 障害児相談支援事業
- 児童自立生活援助事業
- 放課後児童健全育成事業
- 子育て短期支援事業
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 養育支援訪問事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 一時預かり事業
- 小規模住居型児童養育事業
- 小規模保育事業
- 病児保育事業
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
- 助産施設
- 保育所
- 児童厚生施設
- 児童家庭支援センター
- 児童の福祉の増進についての相談に応ずる事業・相談支援事業(特定、障害児)
- 養子縁組あっせん事業
- ひとり親家庭等日常生活支援事業(母子家庭日常生活支援事業)
- 母子・父子福祉施設
- 老人居宅介護等事業
- 老人短期入所事業
- 小規模多機能型居宅介護事業
- 認知症対応型老人共同生活援助事業
- 複合型サービス福祉事業
- 老人デイサービスセンター
- 老人短期入所施設
- 老人福祉センター
- 老人介護支援センター(在宅介護支援センター)
- 障害福祉サービス
- 一般相談支援事業
- 特定相談支援事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム
- 身体障害者訓練事業
- 手話通訳事業
- 介助犬訓練事業
- 聴導犬訓練事業
- 身体障害者福祉センター
- 補装具製作施設
- 盲導犬訓練施設
- 視聴覚障害者情報提供施設
- 身体障害者の更生相談に応ずる事業
- 知的障害者の更生相談に応ずる事業
- 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業(無料低額宿泊所)
- 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業(無料低額診療所)
- 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
- 隣保事業(隣保館)
- 福祉サービス利用援助事業
- 社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
福祉事業所とは
福祉事業とは、社会福祉法第2条に規定された事業のことをいいます。社会福祉法は、1951年に交付された法律であり、社会福祉法人についてや福祉サービスの利用についてなど、社会福祉全般についての規定を定めた法律となっています。
福祉事業は、この社会福祉法2条を根拠とする事業を指しており、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業があります。福祉事業の多くは、施設などに設備や人員の規定が設けられている、また運営には所定の届け出が必要となっています。
その代わり、多くの福祉事業は国からの給付金を受け取ることができるといったメリットがあります。
厚生労働省のページでは下記の様に定義づけられています。
社会福祉事業
社会福祉を目的とする事業のうち、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないものとして、法律上列挙されています。
- 経営主体等の規制があります
- 都道府県知事等による指導監督があります
- 第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類されています
(例)
第1種: 障害者支援施設、重症心身障害児施設、養護老人ホーム等の経営
第2種: 保育所の経営、ホームヘルプ、デイサービス、相談事業
https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-fukushi-jigyou1.html
例えば、子ども食堂やフリースクールといった事業も福祉の役割を持つ事業ですが、これからは社会福祉事業ではないため、誰でも自由に始めることができます。このように法律上では、明確に福祉事業とそれ以外の事業は分けることが出来ます。
第一種社会福祉事業
第一種社会福祉事業は、福祉事業の中でも特に利用者への影響が大きいもので、主に入所施設が該当します。運営主体は、思いに行政及び社会福祉法人に限定されており、都道府県知事への届け出、その他のものが運営する場合は、都道府県知事の許可を得る必要があります。
第一種社会福祉事業の特徴
- 利用者への影響が大きい施設(入所施設等)
- 運営は行政または社会福祉法人、その他の団体は許可を得る必要がある
主な第一種社会福祉事業:救護施設、乳児院、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等
第二種社会福祉事業
第2種社会福祉事業は、比較的利用者への影響が少ない在宅系や訪問系、通所系のサービスが該当します。経営主体に制限はなく、株式会社等の法人でも運営が可能ですが、届出が必要となります。
第二種社会福祉事業の特徴
- 利用者への影響が小さい事業(在宅、通所、訪問等)
- 運営主体に制限はなく、届け出を行うことで運営できる
主な第2種社会福祉事業:児童デイサービス、保育所、老人デイサービス等
第一種社会福祉事業・施設一覧(17事業)
第一種社会福祉事業は、入所施設が中心となっており、運営について利用者への影響が大きい施設となります。そのため、運営主体は市区町村や社会福祉法人が中心となっており、運営には許可を得る必要があります。では、具体的に第一種社会福祉事業にはどういったものがあるのか、全17事業をご紹介します。
生活保護法に基づく事業
まずは生活保護法に規定された事業を紹介します。正確には、生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業であり、救護施設等がこれに当たります。
1.救護施設
救護施設は、生活保護法第38条第2項に規定されており、「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。」とされています。救護施設には特に利用に制限はなく、現在生活が困難であるという方は、どなたでも入所が可能となっています
救護施設は、住居や食事といった生活に必要なサービスに加え、病気を抱えた方のためのリハビリテーションやプログラムを受けることが出来ます。
2.更生施設
更生施設は、生活保護法38条に基づいた施設であり、「生活身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設」となっております。
更生施設は、救護施設とは違い、健康であっても、保護観察処分受けていたり、自分一人での自立が難しい場合に利用されます。住居等の提供に加えて、社会復帰のための就職活動の援助等を受けることが出来ます。
3.医療保護施設
医療保護施設は、生活保護法に38条基づく施設であり、特に医療を必要とする保護者に対して医療の給付を行うことを目的とした施設になります。
主として医療の提供が主であり、保護が必要な方でも特に医療的なケアが必要な方が入居する施設となります。
4.授産施設
授産施設は、生活保護法を根拠とし、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設となっています。
作業を通じて自立のための訓練を受けることが出来ることができます。2006年の障害者自立支援法施行後は、障害者自立支援法に基づき、障害福祉サービスへと移行しました。
5.宿所提供施設
宿泊所提供施設は、生活保護法に基づく施設であり、住居のない要保護者の世帯に対して、住居扶助を行うことを目的とする施設です。
個人だけでなく、世帯も対象としており、あくまでも住居の提供に重きが置かれている点が特徴です。
児童福祉法に基づく事業
児童福祉法においては、児童福祉法に規定す施設を経営する事業が該当します。乳児院や児童養護施設がこれにあたります。
乳児院
乳児院は、児童福祉法37条に規定があり、乳児(孤児)を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設です。
主に1歳未満の乳児を養育しており、住居の提供から日常の世話、食事等の提供を行っています。乳児は、虐待を受けていた子などもいるため、ケアを受けるための専門の職員が配置されています。
母子生活支援施設
母子生活支援施設は、児童福祉法第38条に基づき、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設です。
母子生活支援施設は、児童(18歳未満)および保護者が入所でき、就労や家庭生活について、専門的支援を受けることが出来ます。
児童養護施設
児童養護施設は、児童福祉法41条に基づく施設であり、保護者のいない児童(中略) 虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設であり、1歳以上18歳未満の児童が入所可能です。
児童養護施設では、食事や入浴といった生活面のサポートはもちろん、学習や学校生活に関する相談にものってもらうことができます。
障害児入所施設
障害児入所施設は、児童福祉法に基づいた施設で、障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導および独立自活に必要な知識や技能の付与を行う施設で、 「福祉型」と医療を提供する「医療型」があります。
18歳未満の障害児が入所可能で、衣食住はもちろんのこと、自立に向けた訓練等を受けることが出来、心理士や理学療法士など、専門の職員が配置されています。
児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設)
児童心理治療施設は、児童福祉法43条に基づいた施設で、様々な事情により、心理的な問題を抱え、社会生活への適応が困難となった児童を、入所させ、又は通所により、生活に適応するための訓練や心理療法等を行う施設です。
20歳未満の児童が利用でき、専門のスタッフのもと心理面や生活面のサポートを受けることができます。
児童自立支援施設
児童自立支援施設は、児童福祉法44条に基づく施設であり、犯罪などの不良行為をしたりするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設です。
児童自立支援施設では、生活指導や学習指導、また自立のための共同プログラムなどを受けることが出来ます。
老人福祉法に基づく事業
老人福祉法に基づく第一種社会福祉事業には、養護老人ホーム等があります。
養護老人ホーム
養護老人ホームは、老人福祉法20条に基づく事業であり、環境上の理由と経済的理由により⾃宅での⽣活が困難な65歳以上の⾼齢者が、市区町村の「措置」により⼊所する施設を指します。
養護老人ホームはあくまでも養護、自立支援を目的としているため、介護サービスは受けることが出来ませんが、食事や生活面でのサポート、また自立に向けたプログラムなどを提供しています。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは、老人福祉法20条に基づく施設であり、常時介護が必要な高齢者について、介護サービスや生活面のサポートを提供している施設です。定員が29名以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)と呼ばれます。
特別養護老人ホームは、通常の老人ホームに比べて安価で入居でき、施設の形態としては「多床室」「従来型個室」「ユニット型個室的多床室」「ユニット型個室」があり、入浴、排泄、食事といった日常生活の介護に加え、機能訓練や健康管理を行ってくれます。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームは、老人福祉法20条に基づく施設であり、無料⼜は低額な料⾦で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において⽣活することが困難な⽼⼈を⼊所させ、⾷事の提供その他 ⽇常⽣活上必要な便宜を供与する施設です。
安価に利用できる代わりに、自立度が高い方を対象としており、食事を提供するA型、見守りのみとなるB型、またケアハウスの役割をもつC型があります。基本的な生活のサポートが主となっています。
障害者総合支援法に基づく施設
障害者総合支援法は、正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」といい、平成25年に施行された法律です。これまでの障害者自立支援法が改正され、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、政令で定める難病等により障害がある者で18歳以上の方を対象としています。
障害者支援施設
障害者支援施設は、心身の障害を持つ18歳以上のものにたいして、居住支援や日中活動事業を提供する施設となっており、障害支援区分4以上(50歳以上は3以上)の方が対象です。
入浴や食事、排泄など生活面のサポートから、日中は「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援」といったサービスを受けることができます。
売春防止法に基づく事業
売春防止法は、昭和31年に制定され、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする法律です。売春防止法に基づく事業では、婦人保護施設が規定されています。
婦人保護施設
婦人保護施設は、売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条および配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第5条を根拠に設置される施設で、要保護女子やその同伴児童を保護しています。
住居の提供から、社会復帰のための生活指導や就職指導、食事や衣服の提供等も行っています。
生計困難者に無利子又は低利で資金を融通する事業
生計困難者に無利子又は低利で資金を融通する事業は、社会福祉法2条に規定されている事業であり、生活福祉資金貸付制度として、全国の社会福祉協議会等が実施している。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、社会福祉法2条を根拠とし、生活困窮者に対して、無利子または低利子で資金の貸し付けを行う制度です。
貸付は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯などが対象で世帯単位で行われます。資金の使途については、生活費や就職活動のための費用だったり、介護サービスの利用など、生活の維持のために必要なお金を借りることができ、また制度の利用者は民生委員からの支援を受けることができます。
生計困難者に対して助葬を行う事業
生計困難者に対して助葬を行う事業は、社会福祉法第2条を根拠とし、葬儀にあたり生活保護や生計困難者、また身元不明人などに対し、葬儀を行う事業で、助葬事業として社会福祉法人等が行っています。
助葬事業
助葬事業は、通常の葬祭費用を用意するのが難しい場合に、葬祭事業を行ってくれるサービスです。社会福祉法人や自治体等が、基準額に基づき葬儀を行います。
葬儀費用を払うのが難しい生活保護世帯等が利用することができます。
第一種社会福祉事業一覧表
| 事業・施設名 | 根拠法 | 対象者 | 提供されるサービス |
| 救護施設 | 生活保護法 | 心身の障害により日常生活が困難なもの | 衣食住の確保、リハビリ等 |
| 更生施設 | 生活保護法 | 保護観察処分等で一人での自立が難しいもの | 衣食住の確保、就職活動の援助等のプログラム |
| 医療保護施設 | 生活保護法 | 保護が必要で医療的ケアを要するもの | 衣食住の確保、医療ケア |
| 授産施設 | 生活保護法 | 保護を要するもので就業能力が限られているもの | 自立のための訓練 |
| 宿所提供施設 | 生活保護法 | 住居を必要とする個人、世帯 | 住居の提供 |
| 乳児院 | 児童福祉法 | 保護を必要とする乳幼児 | 衣食住および養育 |
| 母子生活支援施設 | 児童福祉法 | 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童 | 衣食住および就労、家庭相談 |
| 児童養護施設 | 児童福祉法 | 保護者がいない、被虐待児、その他養護を必要とする児童 | 生活面および学習のサポート |
| 障害児入所施設 | 児童福祉法 | 心身に障害をもった18歳未満の児童 | 衣食住および自立訓練、医療ケア等 |
| 児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設) | 児童福祉法 | 情緒面が不安定な20歳未満の児童 | 生活および心理的ケア |
| 児童自立支援施設 | 児童福祉法 | 不良行為等を行う可能性がある18歳未満の児童 | 生活および学習面のサポート、自立のためのプログラム |
| 養護老人ホーム | 老人福祉法 | 心身上の理由により困窮している65歳以上の高齢者 | 衣食住の提供、自立や社会復帰に向けたサポート |
| 特別養護老人ホーム | 老人福祉法 | 常時介護を必要とする65歳以上の高齢者 | 入浴、排泄といった生活面や介護、機能訓練など |
| 軽費老人ホーム | 老人福祉法 | 家庭環境や経済事情から自宅で生活を送ることが困難な高齢者 | 住居の提供、食事や生活面でのサポート |
| 障害者支援施設 | 障害者総合支援法 | 心身の障害により、介護や援助を必要とする。障害者障害支援区分4以上(50歳以上は3以上) | 生活面のサポート、自立訓練や就労訓練など |
| 婦人保護施設 | 売春防止法 | 売春を行う恐れのある要保護女性 | 住居や食事、生活指導、職業指導等 |
| 生活福祉資金貸付制度 | 社会福祉法 | 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等 | 低利子、無利子の資金貸付、相談支援 |
| 助葬事業 | 社会福祉法 | 生活保護世帯、身元不明人等、葬祭費用を用意するのが困難なもの | 葬儀に関わる費用の給付 |
第2種社会福祉事業
第2種社会福祉事業は、社会福祉法に規定される事業の一つであり、第一種社会福祉事業と違い、行政への届け出によって運営することができます。第一種社会福祉事業は、その性質上多くが入所施設となっており、運営が出来なくなった際の利用者への影響が大きいものが多く、ほとんどが社会福祉法人又は行政の運営となっていましたが、第二種の場合は、要件を満たしていれば、株式会社や社団法人などでも運営が可能となっており、多くが通所の施設となっている点が特徴的です。
生計困難者に、その住居で衣食その他日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
生計困難者に、その住居で衣食その他日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業は、社会福祉法第2条に規定があり、生活困窮者に対して住居の提供や相談に応じる事業となります。
無料低額宿泊事業
無料低額宿泊事業は、社会福祉法2条に開設される施設です。入居の対象者は生活困難者となっており、居室の使用料は生活保護の住宅扶助基準以下にしているところが多く、無料または低額にするよう条例で定められている施設が多いです。
家事や食事等の支援を行っている事業所もあり、住居の提供を基本として様々な支援を提供しているのが特徴です。また、老人ホームなどと区分けするために介護や医療に関わるサービスは提供されていないのが基本です。
生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業
生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業は、生活困窮者自立支援法に基づく事業であり、就労訓練事業や、福祉的就労等、就労に関わる訓練や支援を行います。事業を行うには、支援内容が適切であるかどうか都道府県知事の認定をうける必要があります。
就労訓練事業
就労訓練事業は、すぐに一般企業で働くのが難しいという方を対象に、訓練や就労体験など、就労についてのプログラムを提供してくれるサービスです。
被雇用型と雇用型があり、被雇用型は、雇用関係を結ばずに就労訓練を行い、雇用型は雇用関係を結びながら、一般社会での就労を目指します。生活困窮者や生活保護受給者の中で、まだ一般就労が難しいという方が対象となります。
障害児通所支援事業
障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく事業で、障害のある児童や発達に心配がある児童について療育を提供する事業です。放課後デイサービスや児童発達支援としった施設がこの事業に該当する施設となります。
放課後等デイサービス
放課後デイサービスは、児童福祉法第6条に基づく施設であり、支援を必要とする就学児童(小学生~高校生)について、放課後や長期休暇の際に利用できるサービスです。
原則は6歳~18歳までを対象としており、子どもにあわせた個別の支援を行ってくれます。具体的には、機能訓練だったり、ソーシャルスキルなど療育という観点から様々なプログラムが提供されています。利用にあたり、障害者手帳は必要なく、療育の必要性があれば利用することができます。
児童発達支援
児童発達支援は、児童福祉法6条に基づく施設で、支援を必要とする6歳未満の児童に対して、自立支援や機能訓練を提供しています。
集団療育、または個別療育の必要があると認められる児童が利用することができ、食事や着替えなどの日常生活、言語や学校生活に参加、またご家族への支援も行っています。
医療型児童発達支援
医療型児童発達支援は、児童福祉法6条に基づく施設で、児童発達支援にプラスして医療的ケアが加わったサービスとなり、上肢、下肢または体幹機能に障害があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援等が必要と認められた児童が対象となっています。
提供されるサービスは、日常生活へ適応するための訓練に加えて、理学療法や医療的ケアを受けることができます。
居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援は、児童福祉法第6条に基づく支援であり、医療ケアを必要としたり、障害のために、外出することが困難な児童に対して、提供されるサービスとなっています。
重症心身障害児などの重度の障害等であって、児童発達支援等の障害児支援を受けるために外出することが著しく困難な18歳以下の児童を対象に日常生活における基本的な動作や生活のための訓練等を提供しています。
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援は、平成24年の法改正によって創設された障害児通所支援のひとつで、通っている園や学校等に専門職員が訪問してくれるサービスで、保育所や幼稚園、小学校や特別支援学校等への訪問を行ってくれます。
申請を行うのは、施設ではなく障害児の保護者となっており、生活訓練や訪問先スタッフへの指導等を行ってくれます。
障害児相談支援事業
障害児相談支援事業は、児童福祉法に基づく事業であり、「障害児通所申請に係る支給決定前に、障害児通所支援利用計画案等を行うとともに、障害児通所支援利用計画の作成を行う」と定義をもとに展開されている事業になります。
障害福祉サービスを利用するにあたり、児童に対して支援計画の作成等を行い健全な育成をサポートします。障害児通所支援を利用するすべての障害のある児童、保護者が対象で、これからサービスを使う人のための「障害児支援利用援助」とサービスを継続する方のための「継続障害児支援利用援助」の2種類があります。
児童自立生活援助事業
児童自立生活援助事業は、別名自立援助ホームとも呼ばれ、義務教育を終了した20歳未満の児童であり、児童養護施設を退所したもの、または都道府県知事が必要と認めたものに対し、共同生活を営む住居において、相談や日常生活の援助を行うサービスです。
児童自立生活援助では、住居の提供はもちろん、健全な成長のために必要な生活訓練や社会適応のための訓練等を提供しています。
放課後児童健全育成事業
放課後児童健全育成事業は、児童福祉法第6条に基づく事業で、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。
一般的な学童というとわかりやすいと思います。利用対象は小学校に就学している児童で、見守りや遊び、活動の場所などを提供しています。
子育て短期支援事業
子育て短期支援事業は、保護者の方が冠婚葬祭や就労、出産等で一時的に養育できない場合に、児童養護施設等で一時的にお子様をお預かりする事業です。
対象となる児童は、自治体等によっても異なっておりますが、18歳未満の児童までを対象としているところが多いようです。預かりは、夜間にあずかる「トワイライトステイ」、また一時的な入所となる、短期入所生活援助事業「ショートステイ」の2種類があります。
乳児家庭全戸訪問事業
乳児家庭全戸訪問事業は、児童福祉法第6条に定められた事業で、育児に関する相談や子育て支援に関する情報の提供等を行っており、生後4か月までの乳児がいる全ての家庭が対象となります。
出生連絡票を提出するなどの手続きでどなたでも無料で利用することができ、育児に関する様々なサポートを受けることが出来ます。
養育支援訪問事業
養育支援訪問事業は、児童福祉法に基づく事業で、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必要となっている家庭に対して、子育て経験者等による育児・家事の援助又は保健師等による具体的な養育に関する指導助言等を訪問により実施することにより、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図ることを目的としています。
。乳児家庭全戸訪問事業にて、特に養育の必要があると認められた家庭に対して提供され、保健師、助産師、保育士、児童指導員等の専門家より、養育に関する助言や情報提供、相談を受けることが出来ます。
地域子育て支援拠点事業
地域子育て支援拠点事業は、児童福祉法に基づく事業であり、公共施設や児童館等、地域の施設で、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や育児相談ができる場を提供する事業です。
事業には、市町村が中心となって、子育て中の親子の交流を図る「一般型」と、児童福祉施設等が協力する「連携型」の2つのタイプがあります。子育てに関する知識・経験を有する者を配置する義務があり、子育てに関する様々な不安についての相談等を行うこともできます。
一時預かり事業
一時預かり事業は、児童福祉法6条に基づく事業であり、保護者の出産や冠婚葬祭等、一時的に児童の保護が必要な場合に、乳幼児を預けることができるサービスです。
一時預かり事業は、通常の預かりである「一般型」、保育所等で余裕がある場合に利用できる「余裕型」、幼稚園等で行われる「幼稚園型」、訪問にて行われる「訪問型」の4つがあります。
小規模住居型児童養育事業
小規模住居型児童養育事業は児童福祉法第6条に規定された事業で別名ファミリーホームとも呼ばれています。小規模住居型児童養育事業は、家庭で暮らすことが難しい要保護児童を、養育者の家庭にて預けることができるサービスです。
里親として、養育の経験を有する養育者に児童を預け、生活訓練や社会適応など児童の養育を行います。
小規模保育事業
小規模保育事業は、児童福祉法に基づく事業であり、平成27年より新たにスタートした支援事業です。0~2歳児を対象としており、定員6~19名と少人数の預かりになっている点が特徴です。人数等に応じて、A型、B型、C型があります。
利用料は、各自治体が決定しており、小規模ならではのきめ細かい支援が受けられる点を特徴としています。
病児保育事業
病児保育事業は、児童福祉法に基づく事業であり、病気になってしまったり、または病気の回復期等、集団保育が困難な場合に、保育所や病院等で一時的に児童を預かって貰うサービスで、小学生就学時までを主な対象としています。
「病児対応型・病後児対応型」「体調不良児対応型」「非施設型(訪問型)」があり、保育の他に看護も受けられる点に特徴があります。また保育だけでなく看護サービスを受けられるという特徴があります。
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
子育て援助活動支援事業は、児童福祉法に基づく事業であり、ファミリーサポートセンター事業ともいわれています。子育てを希望する地域の子育て世帯や、地域住民のマッチングなど、子育て世帯の支援を行う事業となっています。
乳幼児や小学生等の児童を育てる方は会員となることで、預かりを希望する会員の方に児童を預けることができます。利用方法等は各自治体によっても独自のルールが設けられています。
助産施設
助産施設は、児童福祉法36条に基づく施設で、妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、世帯の経済的な理由により、助産を受けることができない場合に入所し、出産に関する支援をうけることが出来る施設です。
利用方法等は各自治体によって異なりますが、生活保護受給世帯や住民税非課税世帯等、経済的な理由で出産が困難な妊産婦が利用することが出来ます。
保育所
保育所は、児童福祉法に第39条に基づく施設で、保護者が働いている乳幼児(0歳~5歳)を預かる施設です。
保育園というと一番わかりやすいかもしれません。保育所の種類は、保育所と認定こども園があります。
保育所
保育所には大きく分けて3つの施設があり、厚生労働省の基準を満たした「認可保育所」、基準を満たしていない「認可外保育所」があります。また自治体によっては、独自の認証基準を満たすことでえられる「認証保育所」もあります。
認可と認可外では、保育料金を市町村が徴収するのか、施設側に支払うのかといった違いがありますが、職員の配置基準等は同等となっており、認可外保育所の場合は、長時間預けやすいなどの特徴があります。提供しているサービスは保育であり、見守りや遊びが中心となります。
認定こども園
認定こども園は、教育と保育を一体的に行う施設であり、幼稚園と保育園の両方の機能をもった施設となっています。保育園とは管轄省庁も違っていて、内閣府の管轄、認定こども園法が根拠となります。「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4つのタイプがあり、それぞれ機能が異なっています。
保護者が働いている、いないに関わらず利用することができ、預かり時間が幼稚園に比べて長くなっています。
児童厚生施設
児童厚生施設は、児童福祉法40条に基づく施設であり、児童へ健全な遊びを与え、健全育成を図る目的で設置された施設で、乳児から中高生まで、幅広い児童を対象としています。
施設種別としては、「小型児童館」「児童センター」「大型児童館」「児童遊園」といった種別があります。図書館や遊戯室、地域交流の支援、子育て家庭の相談等、児童にまつわる様々な活動を行っています。
児童家庭支援センター
児童家庭支援センターは、児童福祉法44条に基づく施設であり、地域の児童や家庭、地域住民等からの相談を受け付ける施設であり、地域の児童、家庭福祉の向上を目的とした施設です。
市町村からの依頼により、家庭訪問事業や専門家の派遣を行ったり、関係機関と家庭を繋ぐなど、地域と家庭の連携を担う役割があります。
児童の福祉の増進についての相談に応ずる事業・相談支援事業(特定、障害児)
児童の福祉の増進についての相談に応ずる事業・相談支援事業は、子ども・子育て支援法に基づく事業であり、利用者支援事業が行われています。
利用者支援事業
利用支援事業では、子育て家庭や妊産婦が、保育や地域の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等行っています。「基本型」「特定型」「母子保健型」があり、妊産婦や子育て家庭が専門家からのアドバイス等を受けることができます。
養子縁組あっせん事業
養子縁組あっせん事業は、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」に基づいて行われる事業です。事業者は、養子縁組のあっせんにとどまらず、児童や養親希望者の家庭調査、助言等を行います。
民間事業者が、18歳未満の子を養子にすることを希望する者と、養子を養育することを希望する者の間に、連絡や紹介など、養子縁組の成立に必要な媒介的活動を反復継続して行うことを養子縁組のあっせんといい、許可をとることで事業を行うことが出来ます。
ひとり親家庭等日常生活支援事業(母子家庭日常生活支援事業)
ひとり親家庭等日常生活支援事業は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく事業であり、母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、修学等や病気などの事由により、一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員の派遣等を行います。
家庭生活支援員は児童の保育や生活の世話、医療機関との連携を行い、児童と家庭の支援を行います。
母子・父子福祉施設
母子・父子福祉施設は、母子及び父子並びに寡婦福祉法38条に基づく事業であり、母子家庭、または父子家庭に対し、無料、または低額な料金で、母子家庭などに対して各種の相談に応ずるとともに、生活指導や生業の指導、技能の習得、内職のあっせん、保育など、母子家庭などの福祉のための便宜や生活支援を総合的に供与する施設です。
老人居宅介護等事業
老人居宅介護等事業は、老人福祉法に基づく事業であり、65歳以上で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方に対して、自宅で入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活に関する相談・助言等の支援をする事業です。訪問介護や定期巡回といったサービスがあります。
訪問介護
訪問介護は、介護保険法8条に基づくサービスであり、日常生活を送ることが困難となった要介護者に対して、食事の提供や排泄、洗濯、掃除等、生活の手助けを行う事業です。
要介護認定を受けた方が利用でき、軽費老人ホーム等の居室からでも利用することが可能です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護保険法に基づくサービスであり、定期巡回、または通報等により、介護士や看護師が訪問し、入浴、排泄、食事等の提供を行うサービスです。
介護だけでなく看護のサービスを受けることができ、一体型と連携型があり、要介護1以上の認定を受けた方が利用することができます。
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護は、介護保険法に基づく事業で、夜間(18時~8時)において、定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者(要介護者)の居宅を訪問介護員等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護等の提供を行う事業です。
要介護認定を受け、認定を受けた市町村に住んでいる方が利用可能で、利用者の求めに応じて臨時でサービスを受けることも出来ます。
訪問型サービス(第1号訪問介護)
訪問型サービス(第1号訪問介護)は、介護保険法に基づく事業で、居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、その者の居宅において、ケアプランに定められる期間等にわたり、日常生活上の支援を行う事業です。
訪問型サービスはA,B,C,Dと類型が分かれており、要支援認定を受けた方または、チェックリストのサービスの対象となる方が受けることが出来ます。
老人短期入所事業
老人短期入所事業は、老人福祉法に基づく事業であり、介護者の冠婚葬祭、病気等の理由により、一時的に介護が受けられない場合に、養護老人ホームにて、概ね30日を限度として、一時的に対象者を預かってくれるサービスです。
要支援、または要介護認定を受けた高齢者が主な対象となっており、各自治体等が定めた負担額を負担することで、入所中は介護サービスを受けることができます。また、その他介護保険法による短期入所事業も、老人短期入所事業の中に含まれます。
短期入所生活介護
短期入所生活介護は、介護保険法に基づくサービスで、利用者が自宅にて日常生活を営むことが出来るよう、短期入所施設や、特別養護老人ホーム等に短期入所し、施設において、介護や機能訓練といったサービスを受けることが出来る制度です。
要支援、または要介護の認定を受けた高齢者が連続利用日数最大30日を限度に利用することができます。
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護は、介護保険法に基づくサービスで、何らかの事情により自宅での介護が一時的に困難となった場合に、特別養護老人ホーム等に短期間の入所が可能なサービスです。予防に重きが置かれているため、要支援1または要支援2の認定を受けた方が対象となります。
介護予防を目的とし、介護サービスの他に予防に向けた訓練を受けることができ、療養を中心とした介護予防短期入所療養介護という形態もあります。またショートステイ専門の「単独型」と他の施設に併設される「併設型」の2種類のタイプがあります。
小規模多機能型居宅介護事業
小規模多機能型居宅介護事業は、老人福祉法に基づく事業であり、主に中程度以上の介護を必要としている人が、居宅での生活を出来るだけ続けているよう、デイサービス、ショートステイ、訪問を組み合わせ、生活の支援や介護を行うサービスです。事業の中には、介護保険法の小規模多機能型居宅介護などが含まれます。
要支援1~2、要介護1~5の認定をうけた方が利用でき、一つの施設で複数のサービスを受けられるため、利用者の状態を把握してもらいながら、多様なサービスを選択できるメリットがあります。
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護は、介護保険保険法に基づく事業であり、予防を目的とし、デイサービス、ショートステイ、訪問を組み合わせた介護、および機能訓練をうけることが可能なサービスです。サービスの利用により、出来る限り居宅での生活を長く続けていけることを目指します。
介護予防を主な目的としているため、要支援1~2の方が対象となっています。
認知症対応型老人共同生活援助事業
認知症対応型老人共同生活援助事業は、老人福祉法に基づく事業であり、65歳以上で認知症の症状をもつ高齢者に対し、共同生活の場所を提供し、入浴や排泄、生活介護等を提供しています。
一般的にグループホームと呼ばれており、5人~9人の少人数で利用でき、施設の所在地の市町村に住んでいる要支援2以上の高齢者が利用できます。施設として、介護保険法に基づく認知症対応型共同生活介護があります。
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護は、老人福祉法に基づく事業であり、65歳以上で認知症の症状をもつ高齢者に対し、共同生活の場所を提供し、入浴や排泄、生活介護、機能訓練等、認知症の予防を目的としたプログラムを提供しています。
一般的にグループホームと呼ばれており、5人~9人の少人数で利用でき、施設の所在地の市町村に住んでいる要支援2以上の認定を受けた高齢者が利用できます。
複合型サービス福祉事業
複合型サービス福祉事業は、老人福祉法に基づく事業であり、訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによるサービスです。なんらかの理由があり、介護保険法によるサービスが受けられない場合などに利用できます。
対象は、65歳以上で、身体上または精神上の障害があり、日常生活に支障がある方が利用可能で、特に訪問看護も含まれるため、医療的ニーズがある方に適しています。
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護は、介護保険法に基づく事業であり、「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスで、「通い」、「泊まり」、「訪問介護」、「訪問看護」サービスを提供します。
退院後の在宅生活の移行看取り期の支援、家族に対するレスパイト等への対応等、利用者や家族の状態やニーズに応じ、主治医との密接な連携のもと、医療行為も含めた多様なサービスを24時間365日、途切れることなく提供します。要介護1以上の高齢者が利用可能となっています。
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターは、老人福祉法に基づく事業で、在宅で生活している要介護・要支援認定を受けた高齢者の方々に、日帰りで入浴、給食、日常動作訓練などのサービスを行い、高齢者の自立生活を助けるとともに、ご家庭の介護負担をやわらげるための事業です。
介護保険法の老人デイサービスセンターなどがこれにあたります。
通所介護(デイサービス)
通所介護(デイサービス)は、介護保険法第8条に基づく事業であり、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送るため、家族の介護の負担軽減などを目的とています。
施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や介護、機能訓練、食事、交流などのサービスを受けることができ、訪問も利用可能です。要介護以上の認定を受けた高齢者が対象です。
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護は、介護保険法に基づく事業であり、要介護状態となった場合でも、可能な限り居宅において自立した生活を営むことが出来るように生活機能の向上や訓練を行うことを目的とした事業です。
要介護1以上の認定を受けた方が対象で、利用定員が通常の通所介護より少なく、より強い連携の中で合サポートを受けることが出来ます。
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護は、介護保険法に基づく施設であり、認知症の利用者を対象に専門的なケアを提供するサービスです。利用者が可能な限り自宅で生活を続けていけるように、機能訓練を行ったり、介護者や家族の負担軽減のために、一時的に通所する介護サービスです。
認知症の方を対象とした専用の介護施設であるため、認知症の方にあったサービスが受けることができ、「併設型」「単独型」「リビング型」があります。認知症と診断された要介護1以上の方が利用可能です。
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護は、介護保険法に基づく事業であり、軽度の認知症利用者に対し、出来る限り居宅での生活を続けていけるように、予防のための機能訓練等や入浴、排泄といった介護サービスを提供する事業となります。
サービスの特徴といて、要介護状態になることを防ぐことを目的としており、認知症の症状がある要支援1、または2の方が対象となります。
通所型サービス(第1号通所事業)
通所型サービス(第1号通所事業)は、通常のデイサービスと、より細かいニーズに合わせた通所サービスを合わせた総称となります。第一号事業所は、通所介護に加えて、レクレーションや運動などを中心に行う通所型サービスA、住民主体によって運動などを提供する通所型サービスB、市町村の保健師等が機能改善のプログラムを組む通所型サービスCの3つがあります。
第一号通所事業は、要介護、要支援認定を受けた方だけでなく、今後支援や介護が必要となるリスクが高い方も利用することが出来ます。
老人短期入所施設
老人短期入所施設は、老人福祉法に基づく事業であり、一般的にショートステイと呼ばれる事業体です。65歳以上で家族の介護者の疾病などの理由により、在宅介護が一時的に困難となった人や短期入所生活介護を利用する在宅の要介護者に対し、短期間入所や養護を行う施設です。一般に「ショートステイ」と呼ばれ、入浴や食事など日常生活上の世話や機能訓練を行います。
65歳以上で、身体上、または精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障があるとされた場合に利用できます。短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護が含まれます。
老人福祉センター
老人福祉センターは、老人福祉法に基づく施設であり、地域高齢者からの相談に応じ、また健康の増進、教養の向上、レクリエーションのための便宜を総合的に提供し、高齢者に健康で明るい生活を位富ませることを目的としています。
老人福祉センターには、特A型、A型、B型があり、それぞれ役割が異なっています。利用者は各自治体に登録を行うことで利用でき、地区によっては高齢者に限らず、60歳から利用できるとこともあります。
老人介護支援センター(在宅介護支援センター)
老人介護支援センター(在宅介護支援センター)は、老人福祉法に基づく事業で自宅で暮らしている援護が必要な高齢者、必要となりそうな高齢者について、家族からの相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種保険、福祉サービス等の紹介などを行う事業です。
高齢者本人やその家族、地域住民等が無料で利用できます。
障害福祉サービス
障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づいて提供されるサービスであり、障害がある方達に対し、訓練や介護等幅広いサービスを提供します。
就労移行支援や就労継続支援、居宅介護や生活介護等があり「介護給付」「訓練等給付」などの形態があり、給付によって利用手続き等が異なっています。障害がなくても、自治体からの受給者証を交付されることで受けることが可能です。
居宅介護
居宅介護は、障害者総合支援法に基づくサービスであり、居宅にて、入浴、排泄、食事等の介護や調理、洗濯など、介護および生活の支援を受けることが出来るサービスです。
原則として、障害支援区分1以上の認定を受けた方が利用することができます。
重度訪問介護
重度訪問介護は、障害者総合支援法に基づくサービスで、重度の肢体不自由、または重度の知的障害、もしくは精神障害等により、行動上著しい困難を有する障害者で、常時介護を必要とする方に対し、入浴、排泄、着替え等の介助や、移動支援、家事援助、相談等、生活にあたり必要なサービスを提供します。
原則として障害支援区分4以上で、二肢以上に麻痺等がある方が受けることが出来ます。
同行援護
同行援護は、障害者総合支援法に基づくサービスで、移動に著しい困難を有する視覚障害者の方に同行し、移動に必要な情報や、移動の援護、排泄、食事のサポートなどを提供するサービスです。
視覚障害により、移動について困難を有する方で、同行援護アセスメント調査票で1点以上ある方などが利用できます。
行動援護
行動援護とは、行動に著しい困難を有する知的障害者や精神障害等のある方が、行動する際に生じる危険を防止するためにの援護、および介護、排泄のサポートなどを提供するサービスです。
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方が利用できます。
療養介護
療養介護は、障害者総合支援法に基づく事業であり、身体、もしくは精神に障害を持つ方など、著しく重度の障害を持つ方に対して、医療、および常時介護を必要とする方に対して、医療的ケア、および食事、排泄、着替えの介助等、生活のために必要なサポートを提供するサービスです。
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする方で次に該当する方が該当します。
(1) 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方であって、障害支援区分が区分6
(2) 筋ジストロフィー患者または重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上
生活介護
生活介護は、障害者総合支援法に基づく福祉事業であり、常に介護を必要とする方について、主に昼間において、入浴や排泄、食事等の介助をや機能訓練など、生活のサポートに加えて、自立のための訓練等を提供するサービスです。
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
(3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
※ (3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。
・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方が利用できます。
短期入所(ショートステイ)
短期入所(ショートステイ)は、障害者総合支援法に基づく事業で、自宅で介護を行っている方が病気や冠婚葬祭等で介護を出来ない場合に、障害者支援施設等に入所し、入浴、排泄、食事等を受けることができるサービスとなります。
障害支援区分1以上である方、またはそれに該当する児童の方もサービスを受けることができます。
重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援は、障害者総合支援法に基づく事業で、常に介護を必要とする方について、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所等のサービスを提供し、最重度の障害があっても安心して暮らせるように、支援します。
一類、二類、三類があり、常時介護を要する方で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺や寝たきりの状態にある方、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方等がサービスを受けることができます。
自立訓練
自立訓練は、障害者総合支援法に基づく事業で知的障害や精神障害等により、生活が困難な方について、障害者施設や居宅にて、自立のための訓練を提供するサービスです。施設等に長期入院していたなど、生活上の訓練が必要な方など、生活リズムを整える必要がある方を想定しています。
訓練には、身体機能やリハビリなどの機能訓練、また生活に必要な技術などを身に付ける生活訓練があります。18歳~65歳未満で訓練が必要な方が最長で2年間利用できます。具体的には、各自治体での判断となるため、各自治体への確認を行うと良いでしょう。
就労移行支援
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく事業であり、障害者や様々な事情で就労が困難であるものに対して、一般就労に向けて、事業所内での作業や実習、職場探し等、就労への支援を行うサービスです。
最長2年間利用でき、各自治体の判断により、65歳未満で就労を考えている方が利用することが出来ます。障害がなくても、医師等の診断等があれば、サービスの利用が可能です。
就労継続支援
就労継続支援は、障害者総合支援法に基づく事業であり、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者等に向けて、就労の機会を提供し、生産活動やその他の活動の機会を通じて、その知識及び能力向上のために必要な訓練を行う事業です。
事業所と雇用契約を結ぶA型、請負契約となるB型があり、どちらも事業所の支援を受けながら、生産活動を行うことが出来ます。障害者でなくても、医師の診断等、利用が適当と認められ一般就労が困難な方が利用可能となっています。
就労定着支援
就労定着支援は、障害者総合支援法に基づく事業であり、2018年4月に新設された新しいサービスです。就労移行支援、継続支援等を利用して一般就労に移行した方を対象に、就労が継続していけるよう、面談や助言との支援を受けることができます。
就労後、最大で3年6カ月の間サービスを受けることが可能です。(始めの6カ月間は、就労前の福祉サービス事業者からの提供となります)
自立生活援助
自立生活援助は、障害者総合支援法に基づく事業で、自宅で単身などで生活する障害者について、定期的な巡回、訪問、相談対応等を通じて、自立した生活を行っていくことを支援する事業です。障害者の方が孤立せず、また支援を受けながら地域の中で生活してもらうことを目的としています。
利用対象者は、グループホームや精神病院等から一人ぐらいに移行した方など、一人で生活を送っていくことにサポートが必要な障害者が利用出来ます。
共同生活援助(グループホーム)
共同生活援助は、障害者総合支援法に基づく事業で、障害のある方が一軒家やアパートなどにおいて、世話人や生活支援員より、主に夜間に相談、入浴、排泄や食事の介護などの援助を行うサービスです。
定員は10名程度とされており、少人数で共同生活の形を取りながら、地域の中で暮らしていくことができます。65歳未満で障害のある方や入居が必要と認められる方が利用可能です。
一般相談支援事業
一般相談支援事業は、障害者総合支援法に基づく事業であり、障害者当事者や親族、その介護者からの相談について、必要な情報の提供や助言等を行います。支援施設等から地域に移行する方等のための「地域移行支援」、自立して生活するための「地域定着支援」に2種類の形態があります。
施設等から退所する障害者の方、単身で生活をする障害者の方等やその親族等が利用可能です。
特定相談支援事業
特定相談支援事業は、障害者総合支援法に基づく事業であり、障害者がサービスを利用するにあたり、サービス等利用計画の作成をする「サービス利用支援」や、既存のサービスについての見直し等を行ってくれる「継続サービス利用支援」事業があります。
福祉サービスの利用を考えている方、現在利用している方やその家族等が無料で相談にのってもらうことが出来ます。
移動支援事業
移動支援事業とは、障害者総合支援法に基づく事業であり、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出の支援を行うことにより、地域での自立生活や社会参加を助けることを目的とした事業です。
移動支援を利用すると、介護者より移動のために必要な支援や移動中の介助等を受けることができます。重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者等、他の移動支援を受給できる方は対象外となります。
地域活動支援センター
地域活動支援センターは、障害者総合支援法に基づく事業であり、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する施設です。就労支援系と違い、基本日数が決まっていないため、まだ就労が難しいという障害者の方でも、生産活動や創作活動に参加することが出来ます。
障害者手帳を持っている方、または自治体等で利用が適当と認められる方が利用することが出来ます。
福祉ホーム
福祉ホームは、障害者総合支援法に基づく事業で、住居を必要としている障害者に対して、低額な料金で、住居や日常生活についてのサービスを提供しています。
福祉ホームの利用には、ある程度の生活能力がある方が対象となっているため、介護や医療サービスを必要とする方は入居が出来なくなっています。
身体障害者訓練事業
身体障害者訓練事業は、身体障害者福祉法に基づく事業であり、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業です。
身体障害を持ち訓練を必要とする方が利用出来ます。
手話通訳事業
手話通訳事業は、身体障害者福祉法に基づく事業であり、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴
覚障害者等」という。)につき、手話通訳等に関する便宜を供与する事業です。
聴覚障害等により、手話通訳を必要とする方等が利用できます。
介助犬訓練事業
介助犬訓練事業は、身体障害者福祉法に基づく事業です。介助犬とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬を指します。
こちらは訓練事業となり、介助犬に対して訓練を行います。
聴導犬訓練事業
聴導犬訓練事業は、身体障害者福祉法に基づく事業です。聴導犬とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬を指します。
聴導犬訓練事業は、聴導犬を育成する訓練を行う事業となります。
身体障害者福祉センター
身体障害者福祉センターは、身体障害者福祉法に基づく事業であり、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
交流、相談をメインとする「A型」、デイサービスやボランティアの養成等をメインとする「B型」、創作活動や機能訓練をメインとする「デイサービス」、広域利用施設である「障害者更生センター」があります。
補装具製作施設
補装具製作施設は、身体障害者福祉法に基づく事業であり、無料、または低額な料金で、補装具の製作や修理を行う施設のことです。補装具は、身体機能の欠損等を補う、または代替する用具であり、車椅子、杖、義手、義足、下肢装具、眼鏡、補聴器等がこれにあたります。
補装具製作施設では、補装具の製作や修理、使用のための訓練や助言を受けることができ、補装具の必要がある方、相談をしたい方等が利用できます。
盲導犬訓練施設
盲導犬訓練施設は、身体障害者福祉法に定められた事業であり、盲導犬の訓練を行う施設です。盲導犬は、視覚障害により生活や移動について不便を要する障害者を介助するための犬です。
施設では、盲導犬の訓練、育成等を行っています。
視聴覚障害者情報提供施設
視覚障害者情報提供施設は、身体障害者福祉法に基づく事業であり、「点字図書館」「点字出版」「聴覚障害者情報提供施設」があります。
点字図書の貸し出し、出版、制作、聴覚障害者むけのビデオテープの作成等を行っています。
身体障害者の更生相談に応ずる事業
身体障害者の更生相談に応ずる事業は、身体障害者福祉法に基づく事業であり、主に「身体障害者更生相談所」がこれにあたります。身体障害者更生相談所では、身体障害者およびその家族等に対し、専門的知識を必要とする相談、指導、医学的、心理的、職能的判定や市町村に対する助言、指導、巡回相談、地域におけるリハビリテーションの推進等を行っています。
設置主体は、都道府県、政令指定都市となっており、身体障害者の相談事業者として、中核的な役割をもつ事業となります。
知的障害者の更生相談に応ずる事業
知的障害者の更生相談に応ずる事業は、知的障害者福祉法に基づく事業であり、主に「知的障害者更生相談所」がこれにあたります。知的障害者更生相談所では、知的障害者およびその家族等に対し、専門的知識を必要とする相談、指導、医学的、心理的、職能的判定や市町村に対する助言、指導、巡回相談、地域におけるリハビリテーションの推進等を行っています。
設置主体は、都道府県、政令指定都市となっており、障害者の相談事業者として、中核的な役割をもつ事業となります。
生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業(無料低額宿泊所)
生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業とは、社会福祉法に基づく事業であり「無料低額宿泊所」がこれにあたります。
無料低額宿泊所は、無料、または低額な料金(居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下)で、住居を提供します。サービス形態として、宿泊のみ、または食事つき、その他就労に関する相談等にのってくれる宿泊所があり、生活困窮者等が利用できます。
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業(無料低額診療所)
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業は、社会福祉法に基づく事業であり、主として「無料低額診療所」がこれにあたります。
無料低額診療所では、生計困難者等が経済的な理由で医療を受ける機会を失わないよう、無料または低額な料金での診療を提供します。要保護者、ホームレス、DV 被害者、人身取引の被害者など生活困窮者が対象者であり、まずは実施を行っている窓口で相談を受けていただき、利用に適当と判断された場合に、無料または低額診察券が発行され、利用することができます。
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業は、社会福祉法に基づく事業であり、「介護老人保健施設」「介護医療院」がこれにあたります。
生計困難者が経済的な理由によって必要な介護または医療を受ける機会を損なうことがないよう、無料または低額な料金で、介護法人保健施設または介護医療院の利用の機会を提供します。行政の判断により、利用が適当と認められた場合は、無料または低額な料金で施設を利用することが出来ます。
隣保事業(隣保館)
隣保事業は、社会福祉法に基づく事業であり、主として「隣保館」の設置がこれにあたります。隣保館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的とし、市町村が設置主体となります。
地域住民に向けて、生活環境の改善、教育、人権問題の推進といった活動を行っており、地域住民への福祉向上のためのサービスを提供します。主として地域の住民が利用することができます。
福祉サービス利用援助事業
福祉サービス利用援助事業は、社会福祉法に基づく事業であり、判断能力の不十分な人であっても福祉サービスの利用が適切に利用できるよう助け、これに伴う日常的金銭管理等をあわせて行う仕組みです。
社会福祉協議会が実施主体であり、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、行政続き等の利用援助や金銭管理等を提供しています。判断能力が不十分な認知症の方や障害があり、かつ契約内容について判断可能な方が利用できます。
社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業は社会福祉法に基づく事業であり、連絡を行う事業、おおよび助成を行う事業があります。こちらは施設等ではなく、社会福祉事業を行う主体を対象にしているものと思われます。
| 事業・施設名 | 根拠法 | 対象者 | 提供されるサービス |
| 無料低額宿泊事業 | 社会福祉法 | 生活困難者 | 無料または低額で住居を提供 |
| 就労訓練事業 | 生活困窮者自立支援法 | 一般企業等で働くことが難しい人 | 訓練や就労体験など、就労についてのプログラム |
| 放課後等デイサービス | 児童福祉法 | 6歳~18歳で療育が必要と認められる児童 | 機能訓練、社会訓練等、療育のためのプログラムを提供 |
| 児童発達支援 | 児童福祉法 | 6歳未満で療育が必要と認められる児童 | 日常生活や社会生活を送るための療育プログラム |
| 医療型児童発達支援 | 児童福祉法 | 上肢や下肢、および体幹機能に障害を持った児童 | 日常生活や社会生活のためのプログラム、理学療法、医療的ケア |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 児童福祉法 | 、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な児童 | 日常生活における基本的な動作や生活のための訓練等 |
| 保育所等訪問支援 | 児童福祉法 | 学校、保育所等に通う障害児 | 生活訓練、訪問先スタッフへの指導等 |
| 障害児相談支援事業 | 児童福祉法 | 障害児通所サービスを利用する児童、保護者 | 通所サービス利用・継続のための援助計画の作成等 |
| 児童自立生活援助事業 | 児童福祉法 | 義務教育を終了した20歳未満の児童で援助を必要とするもの | 住居および生活訓練や適応訓練、相談等 |
| 放課後児童健全育成事業 | 児童福祉法 | 小学校に就学している児童 | 見守りや遊び、学びの場の提供 |
| 子育て短期支援事業 | 児童福祉法 | 18歳未満の児童 | 短期間の入所、または夜間の預かり |
| 乳児家庭全戸訪問事業 | 児童福祉法 | 生後4か月までの乳児がいる全ての家庭 | 育児相談、子育て支援に関する情報提供等 |
| 養育支援訪問事業 | 児童福祉法 | 養育支援が必要と認められる家庭 | 専門家による養育に関するサポート |
| 地域子育て支援拠点事業 | 児童福祉法 | 子育て中の親子 | 親子の交流や専門員への相談等 |
| 一時預かり事業 | 児童福祉法 | 乳幼児 | 見守り等一時的な預かり |
| 小規模住居型児童養育事業 | 児童福祉法 | 要保護児童 | 里親にて預かり養育を行う |
| 小規模保育事業 | 児童福祉法 | 0~2歳児 | 小規模ならではのきめ細かい保育 |
| 病児保育事業 | 児童福祉法 | 小学生就学時までの児童 | 保育・看護 |
| 子育て援助活動支援事業 | 児童福祉法 | 乳幼児や小学生等の児童を育てる世帯 | 預かり・見守り |
| 助産施設 | 児童福祉法 | 経済的理由により出産が困難な妊産婦 | 助産 |
| 保育所 | 児童福祉法 | 0~5歳の乳幼児 | 保育 |
| 認定こども園 | 認定こども園法 | 0~5歳の乳幼児 | 保育・教育 |
| 児童厚生施設 | 児童福祉法 | 乳児~中高生 | 遊び、地域活動支援等 |
| 児童家庭支援センター | 児童福祉法 | 子育て中の家庭等 | 家庭と地域との連携 |
| 利用支援事業 | 子ども・子育て支援法 | 妊産婦・子育て家庭等 | 子育てについての助言、相談等 |
| 養子縁組あっせん事業 | 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 | 18歳未満の子、および養子を迎え入れるもの | 養子縁組のあっせん、助言 |
| ひとり親家庭等日常生活支援事業 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法 | 母子家庭、父子家庭、寡婦 | 児童の保育、生活支援、連携等 |
| 母子・父子福祉施設 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法 | 母子家庭、父子家庭 | 生活相談、家庭相談、就労支援等 |
| 訪問介護 | 介護保険法 | 要介護認定を受けた者 | 食事、洗濯、掃除等生活のサポート |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護保険法 | 要介護認定を受けた者 | 食事、洗濯、掃除等生活のサポート(定期巡回、または通報により) |
| 夜間対応型訪問介護 | 介護保険法 | 要介護認定を受けた者 | 夜間の定期、また求めに応じた介護サービスの提供 |
| 訪問型サービス(第1号訪問介護) | 介護保険法 | 要介護認定を受けた者、またはチェックリストに該当するもの | 訪問介護サービス |
| 老人短期入所事業 | 老人福祉法 | 要支援、または要介護認定を受けた高齢者 | 30日を限度とした短期入所 |
| 短期入所生活介護 | 介護保険法 | 要支援、または要介護認定を受けた高齢者 | 介護、および機能訓練 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 介護保険法 | 要支援1または要支援2の認定を受けた方 | 介護、および予防のための訓練等 |
| 小規模多機能型居宅介護事業 | 老人福祉法 (介護保険法) | 要支援、又は要介護の認定を受けた方 | デイサービス、ショートステイ、訪問介護 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 介護保険法 | 要支援の認定を受けた方 | デイサービス、ショートステイ、訪問介護を通じた機能訓練、介護予防 |
| 認知症対応型老人共同生活援助事業 | 老人福祉法 (介護保険法) | 要支援2以上、または要介護認定を受けた方 | 共同生活を通じた生活介護 |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 介護保険法 | 要支援2以上、または要介護認定を受けた方 | 共同生活を通じた認知症予防のための機能訓練、生活介護 |
| 複合型サービス福祉事業 | 老人福祉法 | 65歳以上で、身体上または精神上の障害があり、日常生活に支障がある方 | 小規模多機能と訪問看護の組み合わせ |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 介護保険法 | 要介護1以上の高齢者 | 小規模多機能と訪問看護の組み合わせ |
| 老人デイサービスセンター | 老人福祉法 (介護保険法) | 要支援以上の高齢者 | 生活介護、機能訓練等 |
| 通所介護(デイサービス) | 介護保険法 | 要介護以上の高齢者 | 介護、機能訓練、交流、送迎等 |
| 地域密着型通所介護 | 介護保険法 | 要介護1以上の高齢者 | 介護、機能訓練等 |
| 認知症対応型通所介護 | 介護保険法 | 認知症と診断された要介護1以上の方 | 介護、認知症に合わせた機能訓練等 |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の症状がある要支援1、または2 | 介護、認知症予防のための機能訓練 |
| 通所型サービス(第1号通所事業) | 介護保険法 | 要支援、要介護またはそのリスクがあると認められたもの | 住民主体等、地域の支援者による訓練やレクリエーションなど |
| 老人短期入所施設 | 老人福祉法 | 65歳以上で、身体上、または精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障があるとされたもの | 短期的な入所による生活介護、機能訓練等 |
| 老人福祉センター | 老人福祉法 | 利用登録を行った高齢者等 | 各種相談やレクレーション等 |
| 老人介護支援センター(在宅介護支援センター) | 老人福祉法 | 高齢者、その家族、地域住民等 | サービスに関する相談、連絡調整等 |
| 障害福祉サービス | 障害者総合支援法 | 受給者証を交付された者 | 生活介護や自立訓練等 |
| 居宅介護 | 障害者総合支援法 | 障害支援区分1以上の認定を受けたもの | 生活、介護の支援、相談等 |
| 重度訪問介護 | 障害者総合支援法 | 障害支援区分4以上の認定をうけ条件を満たすもの | 生活、介護の支援、相談等 |
| 同行援護 | 障害者総合支援法 | 視覚障害があり、移動に著しい困難を有する方等 | 移動に伴うサポート等 |
| 行動援護 | 障害者総合支援法 | 障害支援区分が3以上で特定の条件に当てはまる方 | 行動の危険の回避、排泄、食事等のサポート |
| 療養介護 | 障害者総合支援法 | 障害支援区分が5以上で特定の条件にあてはまる方 | 医療的ケア、および生活のサポート |
| 生活介護 | 障害者総合支援法 | 障害支援区分が3以上等、特定の条件に当てはまる方 | 食事、排泄等の生活介護、機能訓練、レクレーション等 |
| 短期入所 | 障害者総合支援法 | 障害者支援区分が1以上、または同程度の児童 | 入所施設における短期入所 |
| 重度障害者等包括支援 | 障害者総合支援法 | 常時介護を要する方で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方で特定の条件に当てはまる方 | 居宅介護、重度訪問介護等を組み合わせた包括的な支援 |
| 自立訓練 | 障害者総合支援法 | 18歳~65歳未満で訓練が必要な方 | 生活訓練、機能訓練等、自立生活のために必要な訓練 |
| 就労移行支援 | 障害者総合支援法 | 就労を考えている65歳未満の者 | 作業、実習等、就労、および就労後の定着に向けた訓練 |
| 就労継続支援 | 障害者総合支援法 | 利用が適当と認められ一般就労が困難な方 | 生産機会の提供、および一般就労に向けた訓練 |
| 就労定着支援 | 障害者総合支援法 | 就労移行支援等を利用し一般就労した方 | 就労継続のための助言、面談等 |
| 自立生活援助 | 障害者総合支援法 | 地域での自立生活にサポートが必要な方 | 定期巡回、訪問、生活のための助言、相談等 |
| 共同生活援助 | 障害者総合支援法 | 65歳未満の障害がある方はまたは必要と認められる方 | 主に夜間における食事、生活の相談、援助等 |
| 一般相談支援 | 障害者総合支援法 | 施設等から退所する障害者の方、単身で生活をする障害者の方等やその親族等 | 地域で生活のための必要な情報の提供、相談、助言等 |
| 特定相談支援事業 | 障害者総合支援法 | 福祉サービスの利用を考えている方、現在利用している方やその家族等 | 福祉サービスの利用、見直し等の相談 |
| 移動支援事業 | 障害者総合支援法 | 移動の際に支援を必要とし、条件に該当する障害者 | 移動、および移動中に必要な介助等 |
| 地域活動支援センター | 障害者総合支援法 | 障害者手帳を交付されているもの、または利用が適当と認められるもの | 創作活動、生産活動等への参加、支援 |
| 福祉ホーム | 障害者総合支援法 | 住居を必要としている障害者 | 住居、および生活に必要な支援 |
| 身体障害者訓練事業 | 身体障害者福祉法 | 身体障害があり、訓練を必要としているもの | 身体障害者が日常生活を送るために必要な訓練等 |
| 手話通訳事業 | 身体障害者福祉法 | 聴覚障害、言語障害等により音声での意思疎通が困難なもの | 手話通訳士の派遣、調整等 |
| 介助犬訓練事業 | 身体障害者福祉法 | 介助犬の訓練を行う事業者 | 介助犬への訓練 |
| 聴導犬訓練事業 | 身体障害者福祉法 | 聴導犬の訓練を行う事業者 | 聴導犬への訓練 |
| 身体障害者福祉センター | 身体障害者福祉法 | 身体障害者、およびその家族等 | 交流、相談、創作活動等 |
| 補装具製作施設 | 身体障害者福祉法 | 補装具を必要とする方等 | 補装具の製作、修理、利用についての訓練、助言等 |
| 盲導犬訓練施設 | 身体障害者福祉法 | 盲導犬の訓練を行う事業者 | 盲導犬の訓練 |
| 視覚障害者情報提供施設 | 身体障害者福祉法 | 視覚障害者、聴覚障害者等 | 点字図書の貸し出し、出版、制作、聴覚障害向け出版物の作成等 |
| 身体障害者の更生相談に応ずる事業 | 身体障害者福祉法 | 身体障害者、およびその家族等 | 相談、助言、各種判定、巡回相談等 |
| 知的障害者の校正相談に応ずる事業 | 知的障害者福祉法 | 知的障害者、およびその家族等 | 相談、助言、各種判定、巡回相談等 |
| 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業 | 社会福祉法 | 生活困窮者等 | 住居、食事、就労相談等 |
| 無料又は低額な料金で診療を行う事業 | 社会福祉法 | 要保護者、ホームレス、DV 被害者、人身取引の被害者など生活困窮者 | 無料または低額診察券の発行 |
| 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業 | 社会福祉法 | 生計困難者等 | 無料、または低額な料金での施設利用 |
| 隣保事業 | 社会福祉法 | 地域住民 | 生活環境の改善、相談、教育、人権啓発等 |
| 福祉サービス利用援助事業 | 社会福祉法 | 認知症、障害等で日常生活に不安があり、事業内容を理解可能な方 | 福祉サービスの利用相談、苦情解決、行政手続き、日常金銭管理等 |
| 社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業 | 社会福祉法 | 社会福祉事業の実施主体 | 連絡を行う事業、助成を行う事業 |